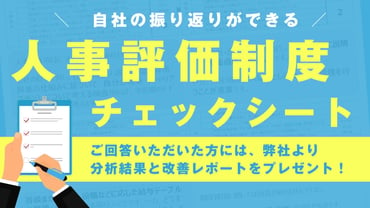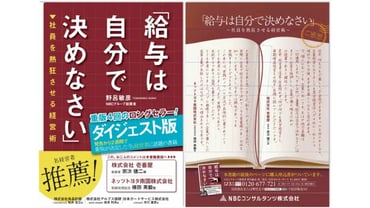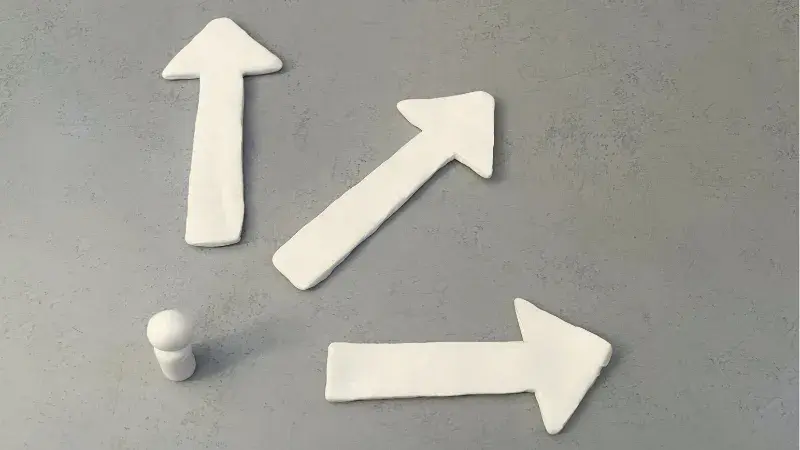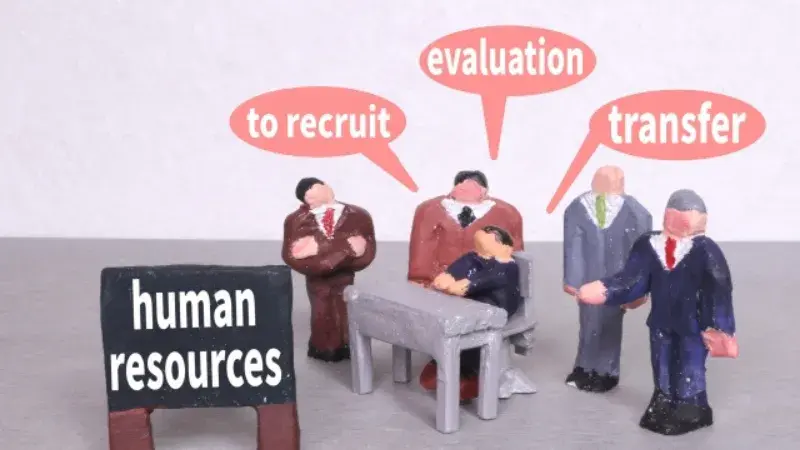弊社で刊行している書籍の中に、「社員は5%しか能力を発揮していない」という衝撃的な一文があります。
社員の潜在能力を引き出す有効な方法として「目標設定」がありますが、うまくできていない企業様を散見します。
そもそも目標が無い、目標はあるが根拠が無い、根拠はあるが適切な形式になっていない、適切であるが進捗管理をしていない……等々。
目標設定について述べるには、より上位概念である組織活性化の三要素(共通目的・目標、意思疎通・コミュニケーション、意欲動機付け)も触れる必要がありますが、この記事でも組織活性化の三要素についても触れていきます。
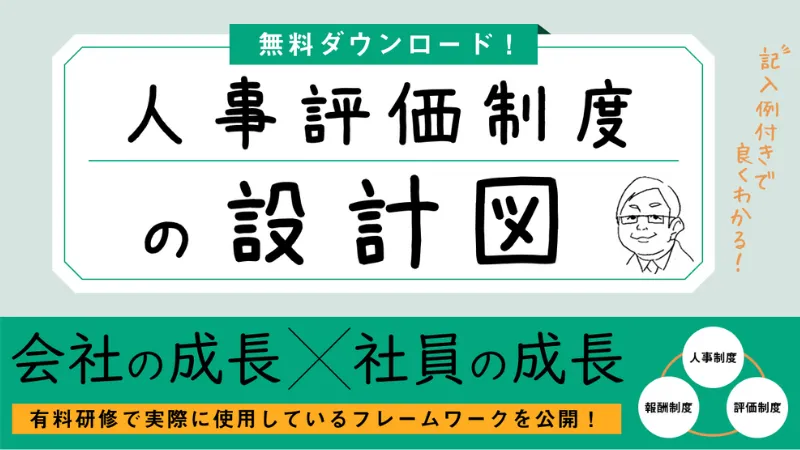
普段、有料の研修でのみ配布しているテンプレ―トをプレゼント!
目次
なお、目標設定について述べるには、より上位概念である組織活性化の三要素(共通目的・目標、意思疎通・コミュニケーション、意欲動機付け)も触れる必要がありますが、この記事でも組織活性化の三要素についても触れていきます。
組織活性化の三要素
組織活性化の三要素を細かく分けると以下のようになります。この三要素が整備・運用されていれば、『どんな組織でも活性化する』という優れものです。ぜひ、御社における整備・運用状況をチェックしてみて下さい。
【1】共通目的・目標
- 共通目的・目標の浸透
- 全社目標利益の浸透
- 部門目標への落とし込み
- 個人目標への落とし込み
- PDCAマネジメントの機能
【2】意思疎通・コミュニケーション
- 共通目標達成のための会議
- 部門間の協力度・交流
- 上下関係
- 本音を言える関係性
【3】意欲動機付け
- 自分の将来の目標
- 仕事のやりがい
- 仲間・上司から認められる風土
- 給与・人事評価制度
なお「目標設定」は【1】に含まれます。
目標を設定する際のポイント
社員が目標を設定する際のポイントは、次の五点です。
- 1.誰が見ても、「その人が何をするのか」がハッキリとわかる形式に すること。
- 2.あとで振り返った時に、「できたか、できなかったか」を客観的に 評価できる形式にすること。
- 3.『頑張って達成できるぎりぎりのライン』に設定する
- 4.期日や数字を用いて具体化する
- 5.設定した目標を達成するためのプロセスが明確
誰が見ても、「その人が何をするのか」がハッキリとわかる形式
1.の理由は、「相互支援・相互牽制」作用を働かせるためです。「相互支援」とは、その人が目標を達成できるように周囲が協力してくれることを意味します。
「相互牽制」とは、その人が目標達成に向けた行動を取っていないと周囲から非難の目が向けられることを意味します。こうして「やらざるを得ない」状況を作り上げます。目標である以上は、絶対に達成する必要があります。
あとで振り返った時に、「できたか、できなかったか」を客観的に評価できる形式
2.の理由は、目標はあとで必ず「評価」をするためです。漠然とした目標では、評価する際に必ず困ります。評価する人によって評価が異なったりもします。
『頑張って達成できるぎりぎりのライン』に設定する
3.の理由は、目標設定は成長のために行いますので、努力せずとも達成できるラインを設定しても意味がありませんし、ひっくり返ってもできないラインを設定しても成功体験にはつながらないからです。
背伸びしてジャンプして、何とか届くラインの設定が重要です。
期日や数字を用いて具体化する
4.の理由は、抽象的な目標ほど意味のないからです。
例えば、「来期は経費を削減する」ではなく、「上半期累計で水道光熱費を昨対5%削減する」とした方が、改善に向けて動き方も変わりますし、なにより達成基準が明確です。
仮に数字化が難しい目標でも、例えば「業務の平準化」ではなく
「作業マニュアルを○月中に完成させ、全員が新たな手順で業務が遂行できる状態を作る」などの
具体的な状態を記すことで具体化が可能です。
設定した目標を達成するためのプロセスが明確
5.の理由は、設定した目標を達成するためのプロセスが明確になっていなければ、
たとえ目標を達成したとしても、「結果論」としての達成では意味は薄れてしまいます。
目標達成するために、何をいつまでにどうするか?この具体的行動計画を明確にし、確実に実行することが必要です。
上記ポイントで磨く力が「目標達成能力」です。結果として目標を達成することが目的ではなく、「目標達成能力」を磨くことが重要なのです。
5W2H
「5W2H」を整えると、上記の<1><2>を自動的に満たすことができます。5W2Hとは以下のことを指します。
- Why(何のために)
- When(いつ、いつから、いつまでに)
- Where(どこで)
- Who(誰が、誰と、誰を)
- What(何を)
- How(どのように)
- How much/many(どの位やるのか)
特に重要なのは以下の三点です。
- When(いつ、いつから、いつまでに)=期限と、
- Who(誰が、誰と、誰を)=責任の所在と、
- How much/many(どの位やるのか)=100点ラインの三つです。
期限を切らなければ人は動きません。責任の所在を明らかにしなければ人は動きません。どの位やるのかを明確にしなければ、達成度を測ることができません。
目標の根拠
人間は目的を求める生き物ですから、何のためにやるのかがハッキリしないと頑張りがききません。そもそも当社の存在意義は何か? 共通の価値観は何か?
すなわち、経営理念等が「共通目的」となり、会社が存続する限り永久に追い続けるものとなります。まずは、それを全社員に浸透させる必要があります。
そして、その目的へ向かう第一歩(階段の一段目)が、今期の全社予算(売上・原価・粗利・人件費・経費・営業利益等)となり、その中で特に重視すべきものが「全社目標利益」となります。
そして、その「全社目標利益」を達成するために 各部門で取り組むものが部門目標」となり、部門ごとの連帯責任となります。さらに、この「部門目標」を部門の社員一人ひとりに分割したものが「個人目標」となります。
つまり、「共通目的」→「全社目標利益」→「部門目標」→「個人目標」が一本線で結ばれ、各自が個人目標を達成すれば部門目標が達成され、全社目標も達成され共通目的に一歩近づく、という関係性が必要なのです。これが「目標の根拠」です。
▼目標設定関連コラム
第1回 目標設定のやり方と5W2H
第2回 間接部門の目標設定
第3回 目標の進捗管理の仕方
第4回 部下の目標達成に導くコーチング
第5回 人事評価のフィードバック方法
第6回 目標設定のステップアップ方法
第7回 目標設定に関する失敗事例
第8回 成功する定量・定性目標設定のポイント
第9回 組織の成熟度に応じた人事評価制度の運用モデル
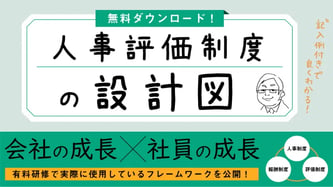
※普段、有料の研修でのみ配布しています!
(令和2年度第3次補正事業再構築補助金により作成)
人事評価制度関連記事
この記事の著者
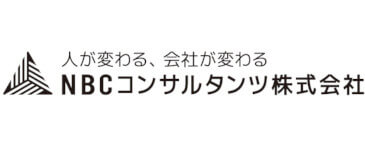
NBCコンサルタンツ株式会社
NBCコンサルタンツ株式会社は1986年の創業以来、会計事務所を母体とする日本最大級のコンサルティングファームとして数多くの企業を支援しております。4,290社の豊富な指導実績を持つプロの経営コンサルタント集団が、事業承継、業績改善、人材育成、人事評価制度など各分野でのノウハウをお届けします。